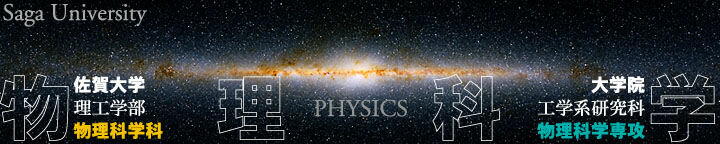OBからのメッセージ
間野 晃充
(2014年度修士 修了)素粒子論グループ
現職:宇宙技術開発株式会社(SED) 第二事業部 衛星技術部 宇宙機エンジニアリンググループ

筑波宇宙センター展示館「スペースドーム」にて撮影
- 1.現在の仕事内容を教えてください。
- 国際宇宙ステーション(ISS)にある「きぼう」日本実験棟で様々な科学実験の運用を行う実験運用管制員の任に就いており、特に、材料物質実験や高エネルギー粒子の観測を主とした運用業務に携わっています。 運用とは、簡単に言うと、「きぼう」にある実験装置に地上から遠隔操作で指令を送り、実験装置から信号を受信して挙動を地上から監視する業務です。例えば、機器が故障した場合などは、宇宙飛行士の安全確保を最優先にしながら装置の安全化・復旧処置を行います。また、本番を模擬した訓練を繰り返し行うことで通常の運用は勿論、想定外の事態が発生した場合でも、迅速に対応できるよう日々訓練を積んでいます。 運用は、8時間交代の3シフト/日で行っております。運用管制員全体の人数は、現在100名程度(SED社員は30名程度)であり、各技術領域や実験領域ごとにチームを編成しています。
- 2.大学で学んだことで現在役立っていること
- 実験運用管制員として、各実験テーマに関する研究者レベルの深い知識は要求されていません。しかし、正しい手順で実験を行うことや不具合発生時の迅速な対処には、研究概要や背景の理解が不可欠です。現在携わっている、材料物質実験や高エネルギー粒子の観測では、運用文書などに物理学の用語が飛び交っていますが、大学時代に、素粒子論をはじめ、物理学全般の基礎を学んだため、スムーズに研究概要や背景を把握することができ、非常に役立っています。 また、宇宙ステーション業務は英語に触れる機会が非常に多いですが、学生時代の海外への短期留学や国際交流活動の経験が役立ち、日々の業務に臆することなく挑めています。
- 3.なぜ物理学科を選んだか
- 高校入学後から物理を学び始めて、基礎物理学から応用物理学まで物理学全般への興味が広がりました。高校2年で素粒子論に関する一般向けの講演を聴講したことをきっかけに、万物の理論の最有力候補と呼ばれている超弦理論の存在を知り、自分自身で自然現象を全て統一的に記述できる理論を構築したいと考え、超弦理論を研究している大学を探しました。 超弦理論を研究している大学というキーワードである程度志望する大学を絞りましたが、その中でも、大学の規模が大きすぎず、先生方と距離の近い環境で学びたいと考え、佐賀大学物理科学科を選びました。結果として、超弦理論を研究している青木先生のもとで学ぶことができ、物理科学科の雰囲気も良く、大学院修了まで充実した学生生活が過ごせました。
- 4.高校生へのメッセージ
- 佐賀大学物理科学科は、先生方との距離が近く、基礎物理学から応用物理学まで幅広く研究が行われていることが特徴だと思います。皆さんの中でまだ、どんな研究をやりたいか分からないが、物理学全般に興味があるという方には、是非入学することをお勧めします。そして、日々の講義や先生方との会話、先輩たちとの交流を通しやりたい研究を見つけて下さい。(もちろん、既にやりたい研究が佐賀大学にある方は、迷わずチャレンジして下さい!)